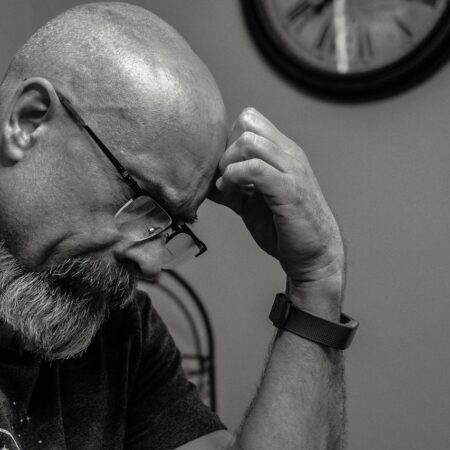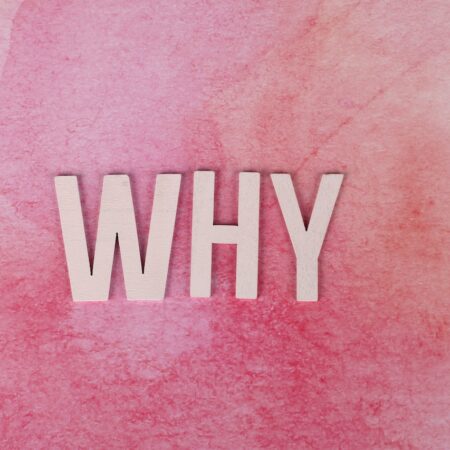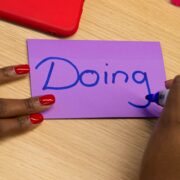「モチベーションの波」を乗りこなすには

みなさんこんにちは。
はるです。
キャリアを歩んでいく、仕事に取り組んでいく上で、誰もが一度は感じること・・それが「モチベーション」の波です。
やる気に満ちあふれて仕事に没頭できる時期もあれば、なぜか手が進まず気力が湧かない、という低調な時期もあります。人間、こうした波があるのは自然なことです。しかし、このモチベーションの波に振り回されすぎると、仕事の継続やキャリア形成に大きな影響が出てしまいます。
ということで、仕事やキャリアにおいて「モチベーションの波」を乗りこなすことがなぜ重要なのか、そしてどうやってその波と付き合っていくのかについて書いてみたいと思います。
まず、なぜ「モチベーションの波」を乗りこなすことが重要なのかということです。
キャリアにおいて重要なのは「持続性」、長期の目線です。短期的には色々な出来事があると思いますが、その一瞬でキャリアや仕事の能力が決まることはありません。たくさんの目の前のことに直面し、一喜一憂しながら歩み、後から振り返った時にまるで轍のようにキャリアは形成されているものです。
しかし、モチベーションは短期間で大きく変動します。したがってモチベーション任せで行動を決めていると、好調な時期にはがんばれる一方で、落ち込んだ時期には何もできなくなってしまいます。そして、それをきっかけに歩みを止めてしまうかもしれません。
そんな経験が飛躍のきっかけになることもあるかもしれませんが、毎度毎度そんな調子では身に付くものも身に付かず、右往左往してキャリアに思い悩んでしまうのではないでしょうか。
キャリアをしっかりと踏みしめ、前に進んでいくためにはモチベーションに振り回されず、波はあれど持続的に前に進んでいくための土台を作ることが重要です。
では、どうすればモチベーションに左右されない土台を築いていけるのでしょうか。
そのためのヒントをいくつかご紹介できればと思います。
「習慣」に落とし込む
非常に有名な話ですが、モチベーションに頼らずに行動を継続するためには、行動を「習慣」に変えるのが一番わかりやすいです。たとえば、「毎朝30分だけ勉強をする」「週に1回は振り返りをする」といったように、小さなルールを生活の中に組み込みましょう。
ある程度強制的に、定例的にルールを作り実践していくことで習慣化され、モチベーションが低い日でも「とりあえずやるか」と体が動くようになります。ちょっと気分が乗らないぐらいでは会社や学校を休んだりしないですよね?ということです。
プロジェクトのマネジメント方法などにも応用されており、日々短時間のデイリーミーティングや週次の振り返りを行うことで、モチベーションに振り回されることなく、その日やるべきことやプロジェクトの課題改善を持続的に実施していけるようになっていたりします。
「やる気が出ない自分」を受け入れる
冒頭でも書きましたが、大前提として、人間のモチベーションは常に一定ではありません。業界のトップを走り続けているような人でさえ、「今日は気が乗らない」と感じる日があるように、私たちにも当然熱量に波があります。
この波は必ずしも怠惰や気合の問題ではなく、体調や気候、人間関係、ライフステージの変化など、さまざまな要因によって引き起こされます。つまり、「やる気が出ない、自分はダメな人間だ」と自身を苛む必要はないということです。
ですので、調子が出ない時の自分を責めるのではなく、「今はそういう時期だな」と一歩引いて見る視点が重要です。
落ち込んでいる時期こそ、自分に向き合い、自分を大切にするタイミングです。「今の自分にできる最小限の行動は何か?」を問い、ほんの少しだけでも前に進めたらそれでいいや、という意識を持ちましょう。そして少しでも前に進んだ場合は自分を褒めてあげましょう。「調子が悪くても前進できる自分」は自信となり、それも習慣化の一つのきっかけとなると思います。
「やりたいこと」より「できること」に注目する
モチベーションが低いときに「やりたいことは何か?」と自問しても、答えは出ないことが多いです。やった方が良いこと(better)や、なりたい自分の理想像なども同様です。理想と乖離している部分に目がいってしまい、さらに落ち込んでしまう可能性もあります。
そんなときは、「今できること」「少しでもできること」「それさえやっておけばいいこと」に目を向けてみてください。
たとえば、仕事をしていても「やればさらに価値を高められること」や「ちょっと先のことだけど今やっておいた方がいいこと」、「すぐに答えがでない難しいもの」などたくさんあると思います。調子の悪い時にそれらのことが頭に散らかってしまうとパニックになってしまいます。
そうなるぐらいであれば、「今はこれさえやっておけば良い」ということに注目し今を乗り切る、これも立派な戦略だと思います。仕事のタスクも俯瞰的に見た上で、自分の調子と相談しながら取り組んでみると良いのではないかと思います。
自分のモチベーションが高まる要因を把握する
モチベーションの低下は、「なぜ今こんなことをしているのだろう?」という、目的を見失っている状態から引き起こされるとよく言われます。確かにそうなのですが、人間なかなか普段からそんな大きな視点でモノゴトを見ていることは多くないと思っています。どちらかといえば、人間はそれぞれモチベーションが湧いてくる要因をいくつか持っており、それを失った時に目的を見失う、そんなパターンが多いのではないでしょうか。
例えば、問題や欠陥がたくさんある状態を改善している時にやる気が出る人や、自分自身の評価が下がらないように維持したい時にやる気が出る人、周りの人から感謝の声が聞けることに対してやる気が出る人、指示をされやらなければならない状態でやる気が出る人、などなど。十人十色で色々あると思います。
モチベーションが下がってしまっている時には、逆にいえばモチベーションが上がる要因が無い状態なのかもしれません。自分自身がどんな時にやる気が出やすいのかを把握し、そんな仕事を積極的に獲得する、仕事にそんな要素を盛り込む、そんなことを意識することで自分でモチベーションをある程度コントロールすることができるのではないでしょうか。
以上、モチベーションに左右されないためのヒントについて書いてみました。
ただし、モチベーションの波は無くすことはできません。無くすという意識ではなく「乗りこなすもの」というイメージです。気持ちが高まったときには思い切って進み、沈んだときにはペースを落として整える。こうした柔軟な対応力こそが、持続的にキャリアを歩んでいくためのコツだと思います。
モチベーションに一喜一憂するのではなく、それを前提として人間は設計されている、と良い意味で諦め、「やる気が出ない時でも前に進める自分なりのやり方」を発見すれば、自身のポテンシャルを発揮して働くことができるのではないでしょうか。
天気が良い日もあれば、荒れる日もあります。でも、自分の舵を自分で握っていれば、どんな波も乗りこなすことができる。そんな心構えを持つことができれば、キャリアはもっと自由かつ納得のできる、力強いものになるのではないでしょうか。
ご一読ありがとうございます。
それでは。